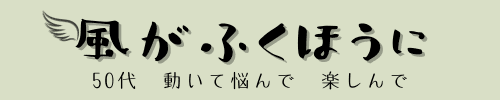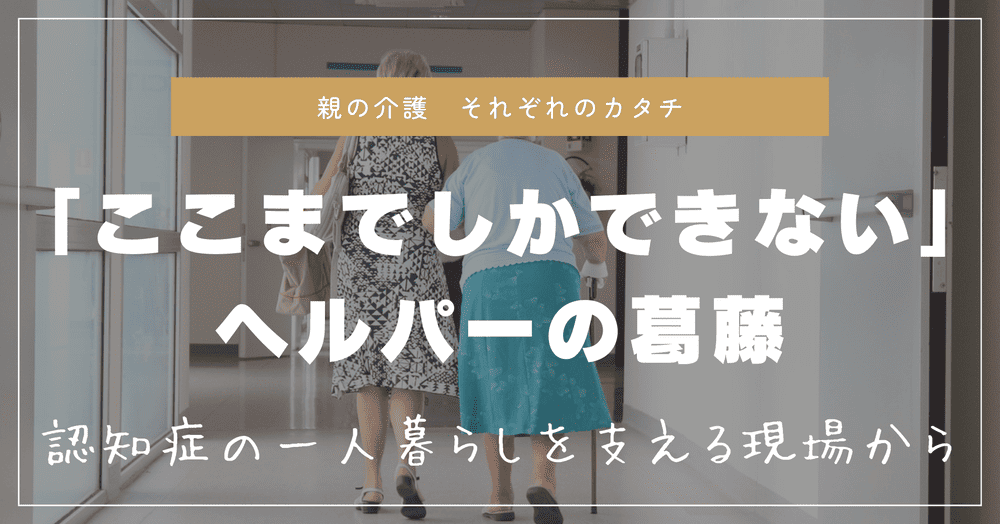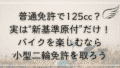「ここまでしかできない」ヘルパーのつらさ|在宅介護の限界と向き合う日々
私がサービス責任者として担当している認知症のお母さんは、今、一人暮らしを続けています。
ご主人はすでに介護施設に入所され、娘さんと息子さんはそれぞれ家庭を持ち、子育て中。
週末には時々来られますが、平日はヘルパーが週2回、訪問しています。
ご家族の主に希望される支援内容は、ゴミ出しと生活状況の把握でした。
話し合いの結果、支援の内容は、ゴミ出し、掃除、食事のセット、服薬の声掛け、そして買い物の代行となりました。
けれど、それ以外の時間、つまり“生活の大半”が、まるで霧の中のようです。
支援中に生活状況を見て、報告するということになりました。
歯みがき、お風呂、食事、服薬――何も「見えない」日常
お母さんは小柄で細身。もともと食の細い方のようです。
火は使えず、電子レンジもほとんど活用できません。炊飯器は時々使いますが、ご飯を炊いたこと自体を忘れてしまいます。
薬も、お薬カレンダーにそのまま残っています。
それでも、「デイサービスには行きたくない」と強く拒否され、お弁当の宅配も受け取りができないと利用されていません。
週2回の訪問時に私たちが食事をセットすると、それは手をつけてくださっているようですが、次の訪問の時には冷蔵庫にカピカピになって残っています。買い物代行の際に、そのまま食べられるものを買っておいています。なのでパンやお菓子で済ませているようです。
歯みがき、お風呂、着替え――生活の基本動作の状況は、ほぼほぼ見えません。
本当は、毎日支援が必要な状態
私は、サービス提供責任者(サ責)なので、たまにしか関わりません。
日頃は、ヘルパーさんからの報告をもらうだけです。
そのヘルパーさんから(通常タブレットで報告)よく電話で「とりあえず〇〇して対処しました。」「○○さん、大丈夫なんですか?」とかかってきます。
当然ですよね。「今日はいいけど、明日は?」って思います。
契約上、一週間にヘルパーの活動時間は2時間。そのほかの時間はほぼ一人で過ごしています。
ですが、認知症とはいっても、何もできなくなるわけではなく、自分時間やペースで生きているって感じです。ですから、お風呂に入らなきゃと思えば、お風呂を入れて入ったり、ごはんを食べたいと思えば、炊飯もできます。食べれるものを探して、食べることができます。
なので、生活はできるのです。
ですが、朝が来たから朝ご飯を食べるとか寝る前に歯を磨こう、洗濯をするとか定期的にできないので、周りから見ると出来ないと判断されます。
ただ、その気分になれば、できるようです。
途中で、忘れたり混乱したりして出来ない場合があります。その頻度が生活力に影響を及ぼすので、注意が必要です。
私はサ責なので、ケアマネに報告して、ケアマネの指示を仰ぐのですが、やはりケアマネも本人や家族の意向で身動きが取れない難しい状況のようです。
客観的に見れば、毎日の支援が必要な状態です。
デイサービスを利用して、訪問介護と組み合わせるのが理想的。
でも現実は、本人の強い拒否、そしておそらく本人の経済的・時間的な事情が絡み、支援は週2回だけにとどまっています。
週末にお子さんが来られるとはいえ、1週間の中で誰にも見守られていない時間が、何日もあります。
カメラを置いたとしても、何ができるのか?
最近は、カメラを設置されるお宅も随分増えました。
認知症の方のお宅は、できればカメラ設置をお勧めしたいです。
安否確認以外に、混乱してやることが分からなくなって止まっている時に、遠隔でも声をかけてあげることができます。
今回の家族の希望である生活状況が知りたいと言うのが、ヘルパーを介さず、自分の目で確認することができます。
ただ、仮に何かを見たとして、家族がそれにどう対応できるのか?
現実には、「見ているだけ」で何もできないかもしれません。
見るのが、怖いと思うかもしれません。
利用者だけでなく家族の気持ちも大切です。よく納得したうえで設置されるといいと思います。
それでも本人は、ぬいぐるみの犬と「のんびり」暮らしている
そんな中でも、お母さんはお気に入りのぬいぐるみ「ポンちゃん」と一緒に、静かに日々を過ごしています。ご機嫌の波はありますが、いつも体調はお変わりなく元気そうです。
訪問のたびに、「この一週間、どうやって過ごしていたんだろう」と思います。
ゴミやお風呂の残り湯、冷蔵庫の中、保存食などを見て、生活ぶりを予想します。
だいたいしか把握できず、心配や不安は尽きません。
でも、本人が笑顔でいる限り、今の暮らしを否定することもできない。
ヘルパーとして関われる範囲は、本当に「ここまで」なんだと痛感します。
答えのない介護支援の中で
在宅介護には、正解がありません。
支援者として、「もっとできることはあるのでは」と思う気持ちと、「これ以上は踏み込めない」という現実の間で、揺れ続けます。
この先、なにが起こるか分からないから怖い。
でも、だからこそ、今日もまた、できることを丁寧に重ねていくしかありません。
まとめ:在宅介護の現実に寄り添うために
在宅での認知症介護には、「支援の限界」がつきまといます。
ヘルパーができること、家族ができること、それぞれに限界があり、全てをカバーすることはできません。
それでも、支援を止めないこと。
「ここまでしかできない」と思いながらも、誰かが見守っているという安心感が、きっとお母さんの生活を少しだけでも支えているはずだから。